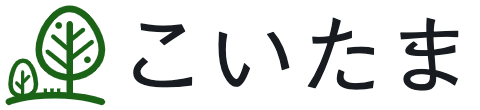瑞穂町郷土資料館「けやき館」(瑞穂町駒形富士山)は、瑞穂町図書館に併設されていた瑞穂町郷土資料館に代わる施設として2014年11月16日に開館した。
けやき館に到着すると、巨大なケヤキの木のふもとにニホンオオカミの像がある。
「なぜ、瑞穂町にニホンオオカミの像が?」
ふと、疑問に思ったこいたま編集部。歴史の紐を解いてみることにした。
絶滅したニホンオオカミ

ニホンオオカミと聞くと、家畜や人を襲う恐ろしい動物と思われがちである。
しかし、農作物に被害を及ぼすシカやイノシシなどを退治してくれるありがたい動物で、農民の守り神として、信仰の対象とされてきた。
昔は、本州、四国、九州などにかなりの数のニホンオオカミが生息していたが、1900年代から始まった自然開発によりニホンオオカミの生息地を奪い、疫病や人間による駆除などが原因で、ついに20世紀初頭に絶滅してしまったと言われている。
瑞穂町でニホンオオカミが捕獲される
瑞穂町長岡には、オオカミの話が伝えられており、同町箱根ヶ崎でもオオカミの鳴き声を聞いたという伝えがある。
同町石畑では、江戸時代末期に民家の縁の下に隠れていたオオカミを、村人である髙橋兄弟が桑畑に追い込んで捕まえたという話がある。捕まえたオオカミの肉は食し、骨は竹やぶに葬り、そこに祠(ほこら)を建てたという。
その時の毛皮と頭蓋骨が代々受け継がれ、今も所蔵されている。特に骨は、「キツネつき(心の病の一種)」という病気に効能があると言われ、お祓い(良くないことを振り払う行為)の道具として使用されたと言われている。
伝承の場としてニホンオオカミ像が建てられる

1969年(昭和44年)2月26日に、考古学者で早稲田大学教授の直良(なおら)信夫氏が鑑定した結果、ニホンオオカミであることが明らかになった。
瑞穂町郷土資料館の開館から半年弱が経過した2015年4月18日に、ニホンオオカミ像を郷土資料館の伝承の広場に建てた。同像は、これらの瑞穂町に伝わる話を参考にして再現したという。
岩の上に登り、「ウォォォーン!」と遠吠えが今にも聞こえそうなほどのリアルな像。こんなに身近な場所にオオカミが生息していたことに驚きだ。
瑞穂町郷土資料館「けやき館」に足を運んだ際は、これらの歴史を思い出しながらぜひご覧いただきたい。
瑞穂町郷土資料館「けやき館」の詳細情報
- 住所:東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山316-5
- 電話:042-568-0634
- 開館時間 : 10:00〜21:00
- 休館日 : 第3月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始・臨時休館日
- 瑞穂町郷土資料館「けやき館」の公式ホームページ