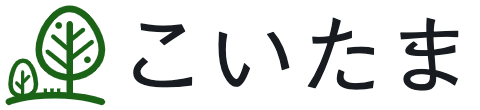日本の食卓に欠かせないワサビは日本原産の野菜のひとつ。強い刺激性のある香味を持つため、根茎や葉は薬味や調味料として使われている。
東京都の最西端に位置する奥多摩町は、水と緑が豊富な地域。生産者は少ないが、傾斜地を利用したワサビ栽培が行われており、同町で栽培されたワサビは「奥多摩わさび」と呼ばれている。
今回は、奥多摩わさびの歴史と特徴、実際に奥多摩わさびを実食した感想をお伝えしようと思う。
奥多摩わさびの歴史

ワサビについては、奈良時代の文献にすでに記載があるが、実際の利用は鎌倉時代、禅宗の寺院に生えていたものを採取し、食用にしたのが始まりと言われている。
奥多摩わさびについては「武蔵名勝図絵」(1823)に奥多摩の地名である「梅沢村」名産と記され、栽培方法のほか「神田青物市場」に出荷されていたと書かれている。古く江戸時代から換金作物として渓流を利用し、各沢ごとに良質なワサビが栽培され、将軍家にも献上されていた。
奥多摩では栽培者の努力により、この地域独特のワサビ田の開発や、「奥多摩一号」をはじめ多くの優良品種を次々と生み出していった。
奥多摩わさびは、昭和40年代までは東京中央卸市場の入荷量で全国3位を誇ったが、作業がすべて手作業と労働が過酷なこと、高齢化により生産者が減少していったという。
現在の日本三大ワサビは、安曇野(あずみの)ワサビ(長野県安曇野市)、有東木(うつろぎ)ワサビ(静岡県静岡市)、匹見(ひきみ)ワサビ(島根県益田市)の3地域といわれている。
東京都は水ワサビの収穫量は全国3位。その9割以上が奥多摩町で収穫されている。水ワサビという分類に関しては、奥多摩がなんとか3大ワサビ圏内に食い込んでいるのが現状だ。
奥多摩わさびの栽培方法

ワサビは冷たくて涼しいところを好む性質。ワサビの生産方法を大別すると主に2種類、畑栽培で育てられる通称「畑ワサビ(陸ワサビ)」と、水栽培で渓流や湧き水で育てられる「水ワサビ(沢ワサビ)」がある。
水栽培は山間部の北斜面で、水が濁らない湧き水地が適している。畑栽培は落葉樹下の夏の日陰で、冬は日が当たる所が選ばれる。
土地の90%以上が森林に覆われた奥多摩町。いわゆる中山間地域と呼ばれるこの場所は、まとまった用地を確保することが困難な地域である。それゆえに、栽培方法のほとんどが水ワサビで、山あいの沢を使って育てられる。
他地域と比べても急傾斜が多い奥多摩では、台風などによる被害を受けやすい。令和元年は台風19号で降った雨水が沢に集中、多くのワサビ田が流されてしまった。
ワサビ農家では復旧を断念する人もいれば、別の地を借りて新たに栽培を始めた人もいる。
奥多摩わさびの特徴

奥多摩わさびの特徴は茎が細長く、キリリとした辛味の中に、ほんのり甘味があり粘り気が強いのが特徴だ。
ワサビは多年草のため、根の部分は一年を通していつでも収穫できる。夏場は辛さが和らぐが、冬のワサビは堅く刺激的な味わいに。最もおいしいワサビの旬は12月~2月頃といえる。
奥多摩のワサビ田の水温は夏場で15度ほど、冬場では3度から5度。凍らないのでワサビ栽培に適している。
奥多摩わさびを実食

丹精込めて育てられた奥多摩わさび。根茎の緑色が濃く、辛み、 香り、外観ともに優れ、生食用として1本2,000円という高値で取引されるという高級品!
ワサビは新葉を伸ばし、外側の古葉を落としながら大きくなる。表面がゴツゴツしているのは葉が落ちた痕跡だ。

最初にワサビのゴツゴツした部分を包丁で削ぎ落とす。それからタワシで皮と汚れを洗い落とし、ごしごしと表面の皮がうっすらなくなるまでこする。

葉の方から、力を入れずに「の」の字を描くようにワサビをすりおろす。さめ肌のようなおろし金がおすすめだ。
ワサビは、きめ細かくするほど辛味が増してくる。ワサビの細胞が壊れることで辛味成分(アリルからし油など)が生成されるためだ。
ワサビ農家の方いわく「先端の方の細胞が古く、茎に近い部分が新鮮。すりおろすと先端の方は元の方に比べざらざらとして粘り気が少なく、黒っぽくて固めのため、茎に近い部分からおろすとよい」とのこと。

奥多摩駅舎2Fのカフェ内で1日限定で販売されていた「奥多摩わさび丼」。たっぷりの風味豊かなかつお節と奥深い味のだし醤油をかけて食べる。
食べた瞬間、ワサビが鼻にツーンッと抜けていき、同時にピリリッと辛みが襲ってくる。すぐに鼻から辛さが抜けていき、次に甘みがやってくる。
食べると辛味、噛むと旨味。交互にやってくる絶妙なバランスが食欲をさらに掻き立てる。
姿形は小さくゴツゴツしていても、その奥に意外な魅力を秘めているのワサビ。東京都にこんなに魅力的な香辛料を栽培している地があるとは、もっと多くの人に認知されてもよいのではないか?
ピリリッと刺激を受けて、和の味に癒やされて。日本人に生まれて良かったと思えた瞬間であった。